更新日: 2025/5/16
連載のねらい
原子吸光分析法(AAS)における検量線の設定って案外悩ましいですよね。AAS における検量線の濃度設定は、ICP-OES や ICP-MS と比べて直線範囲が狭いだけでなく、サンプル濃度を検量線に合わせる“ひと手間”が求められます。そこで本連載では「直線性の基礎」→「直線範囲を外れた場合のリスク」→「最適な濃度設計」の構成で、実データを用いた判断ポイントと対策を解説します。
連載第1回:検量線の“直線性”とは何か?〜信頼できる濃度範囲を見極める〜(本記事)
連載第2回:あの元素の直線範囲は?曲線化の実例とその対策
連載第3回:どう決める?最適な検量線範囲と濃度設計の実践ガイド
フレーム法、ファーネス法ともに同じ課題を持っていますが、今回はフレーム法に焦点を当てて解説します。
なぜ直線性が大事なのか?
AAS における定量分析では、濃度と吸光度が比例関係にある(直線的である)ことが前提となります。これは「ランベルト・ベールの法則(A=εCL)」に基づいています。濃度 C と吸光度 A が比例関係(直線)であることが前提となるため、直線性が崩れると定量誤差が増大します。ε はモル吸光係数、L は単位長さです。
しかしながら、実際の検量線作成では、
- 「どこまでが直線なのか?」
- 「R2 が高ければそれで十分なのか?」
- 「1 点検量線でも大丈夫?」
- 「どうせ曲がるから曲線近似でいい?」
といった悩みや誤解がつきまといます。
1点検量線の限界
たとえば、ゼロ点と標準液 1 点だけで検量線を作成した場合、それは「直線」には見えるかもしれません。しかし、それは“本当に直線性がある”とは言えません。
下図をご覧ください:Mg 285.21 nm を利用しました。
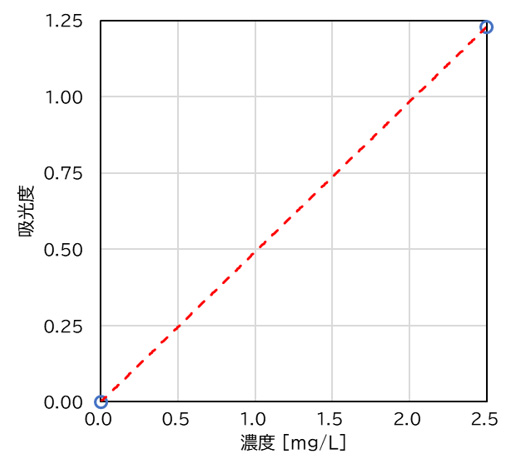
これは、Mg の標準液1(2.5 mg/L)とゼロ点のみを結んだものです(赤点線)。
この 2点では他の濃度でどのような応答を示すかは分かりません。
曲線が確認された範囲の例
次に、複数点(0.05〜2.5 mg/L)をとった検量線(青点線)が以下の通りです。
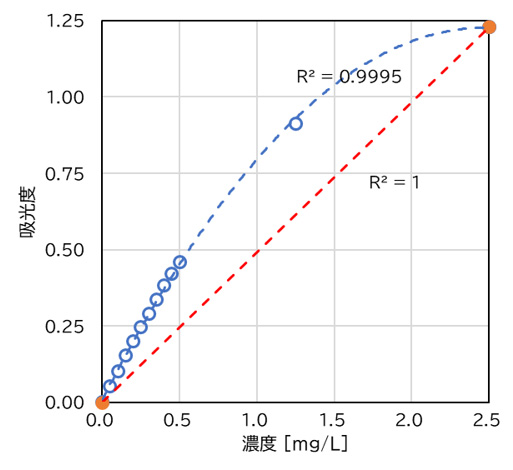
このように二次曲線が得られています。つまり 0 - 2.5 mg/L の間は、実際は曲線関係であり、1点検量線だと大きな誤差を生んでしまう可能性があります。設定した検量線範囲が直線なのか曲線なのかを知るためには、複数点の標準液を測定する必要があります。
今回の Mg の場合は、0 - 0.25 mg/L で一次回帰直線 R2=0.9996 と高い相関が得られる範囲が確認されました(黒実線)。
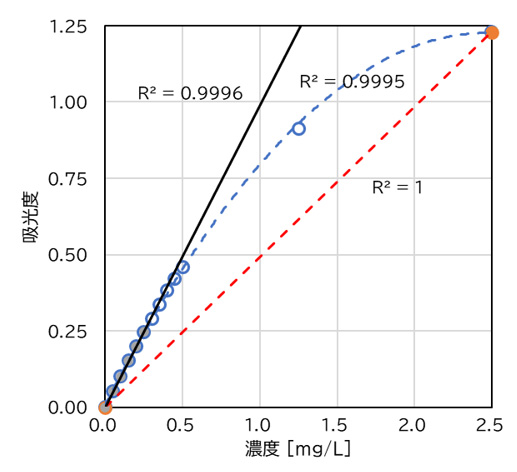
1点検量線vs多点検量線
視覚的にも良好な直線が得られています。
この検量線範囲であれば、標準液各点がきちんと直線上にあることが確認できます。
| 入力濃度 |
吸光度 |
計算濃度 |
誤差 |
| 0 |
0 |
|
|
| 0.05 |
0.0528 |
0.051 |
+3% |
| 0.10 |
0.1006 |
0.100 |
0% |
| 0.15 |
0.1527 |
0.153 |
+2% |
| 0.20 |
0.1996 |
0.200 |
0% |
| 0.25 |
0.2468 |
0.248 |
-1% |
結論:直線性を語るには複数点が必要
「直線性の確認には最低でも原点+3 点以上(推奨:5点)が必要」であり、R2 や誤差を用いた評価が不可欠です。
なお、直線範囲上限の目安はソフト内でも確認することができます。この濃度を目安に標準液を複数濃度で調製し、検量線を実際に測定してみると良いでしょう。

次回は「直線範囲を超えるとどうなる?──曲線化の実例とその対策」を取り上げ、曲線になりやすい Cd や Ni などを取り上げて解説します。
合わせて読みたい記事:
ICP-OESブログ
第15回 検量線の範囲や測定点数に決まりはあるのか?
第27回 検量線の直線性の指標である相関係数って大事ですか?
第51回 多点の検量線を作成すべき時ってどんな時?(検量線の範囲や測定点数の問題について)