分析屋さんが言いたがらない 分析のテクニックあれこれ
2024.4.10更新
ICP-OESにおいて定量値が真値と離れてしまう現象は、標準液とサンプルのマトリックス(共存物質や酸濃度、粘性など)の違いによって起こります。この違いを無くすための有効な方法の1つとして“標準添加法”があります。定量値が妥当になりますよ、という良い話しか聞かないと思います。しかしながら、標準添加法での定量値は、結構ばらつくことが多いです。その理由は、
2024.4.9更新
スペクトルの解析シリーズ第22回、アルミナ・酸化鉄編です。アルミナはアルミニウムの酸化物で、特に有名なのはで、コランダム結晶構造を持つ α-アルミナ(α-Al2O3)です。酸化鉄 (III) も同様にコランダム構造ですが、互いに異なる吸収ピークを持ちます。両者は樹脂に添加されることがあるため、異物として検出されることがあります。本エントリではこれらの酸化物をFTIRで分析/解析する際に役立つ情報をお届けします。
2024.4.9更新
ディスクリミネーションの対策法の一つとして、サンドイッチ法をご紹介しました。
今回は、オートサンプラーを活用したサンドイッチ法と、PerkinElmerの新製品・GC2400のオートサンプラーの特徴も併せてご紹介します。
その他のブログはこちらから >
 ここ数年、世界的にヘリウムガスの供給が困難な状況にあり、安定してヘリウムガスを使用することが、難しくなっています。
ここ数年、世界的にヘリウムガスの供給が困難な状況にあり、安定してヘリウムガスを使用することが、難しくなっています。
パーキンエルマーでは、ICP-MS、GCにおける代替案をご用意しております。
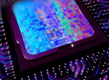 NexION 5000は、真のトリプル四重極を搭載した初めてのマルチ四重極ICP-MSシステムです。半導体業界等で要求される厳しい微量元素分析ニーズ対して、NexION5000 に搭載された 4 つの四重極の機能やこの機能を利用した応用例と有用性について「オンデマンドe-ライブラリー」をご用意致しました。高分解能形ICP-MSや従来のトリプル四重極ICP-MSを超えて、卓越したバックグラウンド相当濃度 (BEC) と優れた安定性を提供します。
NexION 5000は、真のトリプル四重極を搭載した初めてのマルチ四重極ICP-MSシステムです。半導体業界等で要求される厳しい微量元素分析ニーズ対して、NexION5000 に搭載された 4 つの四重極の機能やこの機能を利用した応用例と有用性について「オンデマンドe-ライブラリー」をご用意致しました。高分解能形ICP-MSや従来のトリプル四重極ICP-MSを超えて、卓越したバックグラウンド相当濃度 (BEC) と優れた安定性を提供します。
従来のICP-MSを超えるこの性能をぜひ体験してください。
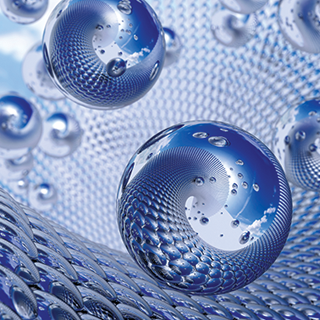 最先端の技術であるナノテクノロジーは、急速に成長しています。またライフサイエンスの領域では、一細胞単位でのシングルセル解析技術に大きな注目が集まっています。
最先端の技術であるナノテクノロジーは、急速に成長しています。またライフサイエンスの領域では、一細胞単位でのシングルセル解析技術に大きな注目が集まっています。
NexION 2000はこれらのナノマテリアルや単一細胞の分析を行うために必要な要件を満たしており、新たなアプリケーションニーズに貢献します。